EVENT REPORT イベントレポート
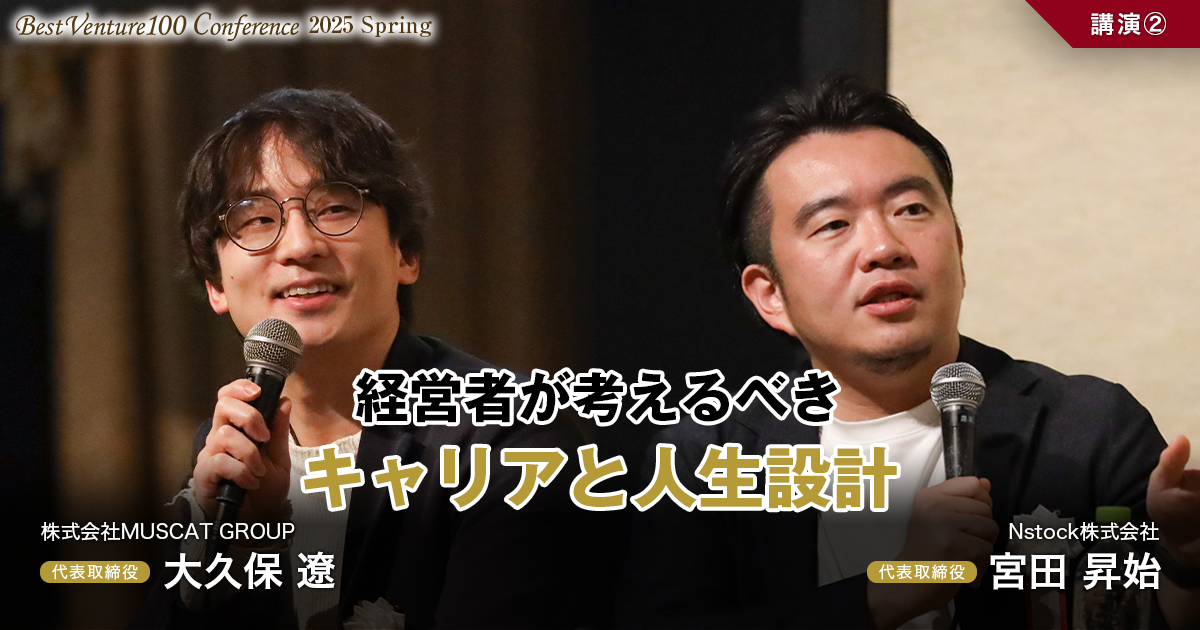
【ベストベンチャー100カンファレンス 2025 Spring 講演②】経営者が考えるべきキャリアと人生設計
Nstock株式会社 代表取締役 宮田 昇始 / 株式会社MUSCAT GROUP 代表取締役 大久保 遼
これから成長が期待されるベンチャー企業を厳正な審査の下に100社選出する『ベストベンチャー100』。その選出企業を始め、完全招待制でベンチャー企業の経営陣に参加を呼びかけ、2025年3月18日に『ベストベンチャー100カンファレンス2025Spring』を明治記念館で開催した。第一部の講演では、日本を代表するベンチャーの経営者が登壇。今回は、「経営者が考えるべきキャリアと人生設計」をテーマに、Nstock株式会社代表取締役の宮田昇始氏と、株式会社MUSCAT GROUP代表取締役の大久保遼氏が行った講演の内容をレポートする。
自己紹介
宮田:SmartHRの創業者で、いまはNstockの代表取締役を務めている宮田と申します。私は12年前に友人とSmartHRを起業し、その2年後に人事労務クラウドサービス「SmartHR」をリリースしました。おかげさまで急成長でき、サービス開始から6年で時価総額1,000億円を超えて、ユニコーン企業になれました。ただ、いろいろ思うこともあって、3年前にSmartHRの社長の座を後進にバトンタッチし、私はNstockという新しい会社を始めました。Nstockでは、ストックオプションなど株式報酬における運用・設計の課題を解決し、その本来のポテンシャルを最大限に引き出すために開発した「株式報酬SaaS」を提供しています。ストックオプションをより機動的に活用して、その価値を社員に感じてもらえるようなサービスです。また、セカンダリー事業として、スタートアップのための、非上場株式の取引所設置を準備しています。社員や創業者、初期の投資家が株式を売却できるようなプラットフォームです。SmartHRも2024年、セカンダリーで約114億円の株式を売却しました。これらの大半は投資家ではなく、私を含め当社の初期メンバーが所有していた株式。スタートアップで働いている人が、このように夢のあるセカンダリーを励みにしてもらえるようプラットフォームの事業化を目指しています。
大久保:MUSCAT GROUP代表取締役の大久保です。私は、もともと証券会社にいましたが、その後、オンライン広告テクノロジー企業のMomentumを立ち上げました。それを3年弱で、SupershipというKDDIのグループ会社に売却。ただ、「自分が起業した会社でIPOを目指したい」という想いがあり、MUSCAT GROUPを2016年に創業。2024年6月に念願の東証グロースに上場しました。MUSCAT GROUPでは、「マーケティングソリューション事業」をメインに手がけ、SNSを中心にBtoBのマーケティング支援を行っています。売り上げの4割を占めるのは同事業ですが、今、成長戦略のドライバーとして位置づけているのは、「ブランドプロデュース事業」です。世のなかで隠れた良い商品やIP、技術力を持つメーカーを買収して、私たちのブランドプロデュース力で自社ブランドとして展開することに力を入れています。特に「MiiS」という、オーラルケアやホワイトニング、口臭ケアのブランドが成功。この成功事例をもとに社内で確立した「MiiSモデル」を、M&Aによってグループインしてもらった別のブランドに適用しています。また、松村商店というキッズ・ティーンズ向けオリジナル服飾雑貨を40年以上展開しているメーカーを2024年に買収しました。松村商店オリジナルのスクールバッグブランド「ロコネイル」には高いポテンシャルがあるにもかかわらず、活用されていない状態でした。そこで我々が、「ロコネイル」のブランドプロデュースを強化した結果、TikTokでバズらせることに成功したのです。このほかにも、電動アシスト自転車ブランド「MOVE.eBike」など、さまざまなブランドがありますが、当社は「ニッチトップ戦略」をとっています。ECに限らず、卸先の店舗や自社店舗といったオフラインの販路も含めて、売り上げを伸ばすために取り組んでいます。BtoBのマーケティング支援も展開し、おもに日用品や食料品のナショナルブランドメーカーのクライアントに強いのが、競合に対する当社のポジショニングになっています。
大久保:MUSCAT GROUP代表取締役の大久保です。私は、もともと証券会社にいましたが、その後、オンライン広告テクノロジー企業のMomentumを立ち上げました。それを3年弱で、SupershipというKDDIのグループ会社に売却。ただ、「自分が起業した会社でIPOを目指したい」という想いがあり、MUSCAT GROUPを2016年に創業。2024年6月に念願の東証グロースに上場しました。MUSCAT GROUPでは、「マーケティングソリューション事業」をメインに手がけ、SNSを中心にBtoBのマーケティング支援を行っています。売り上げの4割を占めるのは同事業ですが、今、成長戦略のドライバーとして位置づけているのは、「ブランドプロデュース事業」です。世のなかで隠れた良い商品やIP、技術力を持つメーカーを買収して、私たちのブランドプロデュース力で自社ブランドとして展開することに力を入れています。特に「MiiS」という、オーラルケアやホワイトニング、口臭ケアのブランドが成功。この成功事例をもとに社内で確立した「MiiSモデル」を、M&Aによってグループインしてもらった別のブランドに適用しています。また、松村商店というキッズ・ティーンズ向けオリジナル服飾雑貨を40年以上展開しているメーカーを2024年に買収しました。松村商店オリジナルのスクールバッグブランド「ロコネイル」には高いポテンシャルがあるにもかかわらず、活用されていない状態でした。そこで我々が、「ロコネイル」のブランドプロデュースを強化した結果、TikTokでバズらせることに成功したのです。このほかにも、電動アシスト自転車ブランド「MOVE.eBike」など、さまざまなブランドがありますが、当社は「ニッチトップ戦略」をとっています。ECに限らず、卸先の店舗や自社店舗といったオフラインの販路も含めて、売り上げを伸ばすために取り組んでいます。BtoBのマーケティング支援も展開し、おもに日用品や食料品のナショナルブランドメーカーのクライアントに強いのが、競合に対する当社のポジショニングになっています。
起業家の“裏の欲望”とは
宮田:今回、「こんなテーマで話したら、面白いんじゃないか」ということで提案したのが「起業家の“裏の欲望”とは」です。起業家は、目的があって創業したはずなのに、会社が大きくなると、いろいろなしがらみが増えて、「自分は、そもそも何がしたかったのだっけ」と立ち止まる瞬間が少なからずあるのではないでしょうか。私もそうでした。起業家には「表向きの目的」があり、私の場合は「スタートアップ業界を良くしたい」です。一方、誰でもそれとは違う「裏の目的」を持っているらしいんですね。私はここ数年で、自分の「裏の目的」がはっきりしてきました。少し恥ずかしいですが、それは「身近な人に褒められたい」です。その目的に忠実に生きようと、起業2社目のNstockでは、「自分の本当にやりたいこと」にフィットする事業や組織作りを考えました。このように「裏の目的」を知っておくと、自分が嫌だと思う方向に会社を導かなくて済むと思います。
大久保:「裏の目的」は、正直言いづらいですよね。当社の「表向きの目的」は、「成熟市場に埋もれた成長領域を探して、伸ばしたい」です。私個人の「裏の目的」は、宮田さんとは逆で、「知らない人に褒められたい」です。たとえば、ヒットブランドを出したときに、まったく面識のない若い人に褒められると結構スカッとするものがあります。これは「裏の欲望」なんだろうなと思っています。
大久保:「裏の目的」は、正直言いづらいですよね。当社の「表向きの目的」は、「成熟市場に埋もれた成長領域を探して、伸ばしたい」です。私個人の「裏の目的」は、宮田さんとは逆で、「知らない人に褒められたい」です。たとえば、ヒットブランドを出したときに、まったく面識のない若い人に褒められると結構スカッとするものがあります。これは「裏の欲望」なんだろうなと思っています。
人生の変遷と幸福度(幼少期から起業まで)
宮田 私の子ども時代、実母が家にいない時期がありました。4~6歳の頃です。コーチングの理論によれば、「7歳までの体験が、人格の半分を決める」とのこと。ですから、おそらくこの「母の不在」が私の人格形成に強烈に影響を与えた体験だったと思っています。この時期、母と会えるのは1年に1度ぐらい、しかも会えたとしても、車の窓ガラス越しに話す程度でした。当時は、「母親がいない状態でどうやって今後生き延びていくか」と不安を感じたことをよく覚えています。ただ、昔は、自分の「裏の目的」をはっきりと意識していなくて、「誰に認められたいか」もわかっていませんでした。しかし、振り返ると、「やっぱり身近な人に認められたかったんだな」と感じるのです。かつては、新卒の同期に認められたかったですし、起業してからは、同じタイミングで起業した人や先輩の起業家に認められたかったです。身近なパートナーに認められたいとも思いましたね。「相手の名前や顔をよく知っていて、ときには頼れる関係性の人に認められたい」という気持ちが強かったのです。その気持ちが起業を目指す動機にもつながったのかなと思っています。
大久保:恵まれた家庭で育ったので、幼少期の幸福度は高かったです。少年期も楽勝な感じでスイスイと東大合格までは行きました。ただ、入学後は「東大生って、『東大』を取ったら何も残らないじゃん」と言われて、悔しく感じるときがありましたね。そこから、「経歴以外で評価されたい」という願望が生まれて、「それなら、起業してやろう」と考えるようになりました。ところが、最初の起業は、よく研究もせずに走り出したため、うまくいきませんでした。そこで、いったん起業はあきらめ、2012年に大学を卒業した後は、ゴールドマン・サックス証券に入社しました。幸福度の面では、この時代は非常につらかったです。投資銀行部門でM&Aを担当していたのですが、当時、外資系の金融会社は朝3~4時まで働くのが当たり前。甘い「お坊ちゃまマインド」をすべて叩き壊されました。それもあって、「もう1度起業すれば、今度は成功できるんじゃないか」という欲や情熱が、湧き上がったのです。
大久保:恵まれた家庭で育ったので、幼少期の幸福度は高かったです。少年期も楽勝な感じでスイスイと東大合格までは行きました。ただ、入学後は「東大生って、『東大』を取ったら何も残らないじゃん」と言われて、悔しく感じるときがありましたね。そこから、「経歴以外で評価されたい」という願望が生まれて、「それなら、起業してやろう」と考えるようになりました。ところが、最初の起業は、よく研究もせずに走り出したため、うまくいきませんでした。そこで、いったん起業はあきらめ、2012年に大学を卒業した後は、ゴールドマン・サックス証券に入社しました。幸福度の面では、この時代は非常につらかったです。投資銀行部門でM&Aを担当していたのですが、当時、外資系の金融会社は朝3~4時まで働くのが当たり前。甘い「お坊ちゃまマインド」をすべて叩き壊されました。それもあって、「もう1度起業すれば、今度は成功できるんじゃないか」という欲や情熱が、湧き上がったのです。
人生の変遷と幸福度(起業後のターニングポイント➀)
宮田:SmartHRでは当初、『SmartHR』以外のサービスで起業しました。起業後は、2年ほどピボットを繰り返し、その間は、サービスをリリースしても、「リアクションがない、誰にも使ってもらえない」といった感じで、結構しんどい時期でした。しかし、『SmartHR』をリリースして以降は、面白いように事業が伸びたのです。特に創業期から従業員が100名ぐらいまでの期間は、すごく楽しく仕事ができました。SmartHRの創業後数年間は、とても仲の良い人たちと、明確で大きな目標に向かってがんばることができました。「人付き合いの苦手だった子どもの頃に味わえなかった青春を取り戻している」という感覚がすごくありました。ただ、ある時期から様子が変わり、会社のことをどんどん嫌いになっていったのです。それまで、社員と仲良く働く時間が、私としては非常に重要でした。しかし、会社が大きくなってくると、新しい社員には、そうした態度がえこひいきに映ったようで、「昔のメンバーとばかり仲良くしないでください」、「飲み会は自粛してください」と言われるようになりました。社員との楽しい時間を奪われることは、すごくつらかったですし、行動を制限されるような感じがしました。徐々に、自分の本来の生活圏から距離が遠い人たちに向けてサービスを提供したり、メッセージを届けるといった仕事が増えてきて、「これは本来やりたかったことじゃない」とも感じるようになったのです。
大久保:最初に起業したMomentumでは当初、BtoC事業を手がけていました。しかし、私がBtoCの事業センスに乏しかったため、成長させることができず、ピボットとして、ゴールドマン・サックス時代に温めていたアイデアの1つを形にしようと考えました。それが、不適切なサイトなど、広告主のブランド価値の毀損を招くサイトへの広告出稿を回避するツールです。ただ、それも「長期戦で育てていく事業ではない」と判断して、結局、Momentumは売却。2社目に立ち上げたのがMUSCAT GROUPです。私は「社会課題を解決したい」という強烈な意識を持つタイプの起業家ではありません。ですから、MUSCAT GROUPはある程度、IPOを念頭に起業し、結果的に東証グロースに上場することができました。
大久保:最初に起業したMomentumでは当初、BtoC事業を手がけていました。しかし、私がBtoCの事業センスに乏しかったため、成長させることができず、ピボットとして、ゴールドマン・サックス時代に温めていたアイデアの1つを形にしようと考えました。それが、不適切なサイトなど、広告主のブランド価値の毀損を招くサイトへの広告出稿を回避するツールです。ただ、それも「長期戦で育てていく事業ではない」と判断して、結局、Momentumは売却。2社目に立ち上げたのがMUSCAT GROUPです。私は「社会課題を解決したい」という強烈な意識を持つタイプの起業家ではありません。ですから、MUSCAT GROUPはある程度、IPOを念頭に起業し、結果的に東証グロースに上場することができました。
人生の変遷と幸福度(起業後のターニングポイント➁)
宮田:スタートアップ業界向けで事業を行うNstockを始めてからは、楽しく仕事ができています。自分の「裏の目的」に近い形で事業を作れているからだと思います。スタートアップ業界で働く人は、自分にとっては「身内」に近い感覚で、「業界のここが課題だよね」と話をしても通じるような人たち。そのため、Nstockの事業の構造を話すと、「同じ課題を感じていました」と共感してもらえるので、事業をやっていてすごく楽しいです。「身近な人に認められている」という感覚がとてもあるのです。今、SmartHRの社員数は約1,400名に膨らんでいます。一方、Nstockは、自分が「楽しい」と思えるぐらいの組織規模で働き続けられるよう、社員数が150~200名程度で収まるビジネスモデルを意識しています。
大久保:MUSCAT GROUPはSNSマーケ支援事業で成長し、IPOも実現できたのですが、上場後は株価が伸び悩みました。そこで、巻き返しを図るため、思い切って成長ドライバーを、祖業のSNSマーケ支援からブランドプロデュース事業に位置づけ直すことにしたのです。ブランドプロデュース領域では、M&Aによってグループインしてもらったメーカーとのコラボによって、複数ブランドを開発できるのが強みとなり、実績も出てきました。その結果、株価は低迷から脱することができ、海外投資家にも注目されるようになりました。
大久保:MUSCAT GROUPはSNSマーケ支援事業で成長し、IPOも実現できたのですが、上場後は株価が伸び悩みました。そこで、巻き返しを図るため、思い切って成長ドライバーを、祖業のSNSマーケ支援からブランドプロデュース事業に位置づけ直すことにしたのです。ブランドプロデュース領域では、M&Aによってグループインしてもらったメーカーとのコラボによって、複数ブランドを開発できるのが強みとなり、実績も出てきました。その結果、株価は低迷から脱することができ、海外投資家にも注目されるようになりました。
参加者へのメッセージ
宮田:会場の経営者の皆さんは、やりたいことがあって自分の会社を立ち上げたのだと思います。ただ、会社が大きくなると、思っても見なかったしがらみが生じて、想定外の方向に事業や組織が向かうことがあると思います。そのようなときは、「なんでこんなことやっているんだっけ」と思うかもしれません。しかし、自分の「裏の目的」が明確であれば、がんばり続けられると思います。皆さんも、「自分の『裏の目的』はなんだろう」と自問したり、経営メンバーの「裏の目的」がわかったりすると、経営がすごく面白くなると思います。
大久保:経営者としてのキャリアの築き方や、経営のやり方には、「これが正解」というものはありません。その時々の自分にとっての「正解」を、自分で探し続けていく必要があります。「経営者はこうあるべき」といった周囲の声に流されそうになることもありますが、大切なのは、自分の中で「自分なりの経営者像」をしっかり持つことだと思います。そして、「こういう経営スタイルでいこう」という自分なりの軸を持ち続けることによって、結果として成功に近づくことができるのではないかと思っています。
大久保:経営者としてのキャリアの築き方や、経営のやり方には、「これが正解」というものはありません。その時々の自分にとっての「正解」を、自分で探し続けていく必要があります。「経営者はこうあるべき」といった周囲の声に流されそうになることもありますが、大切なのは、自分の中で「自分なりの経営者像」をしっかり持つことだと思います。そして、「こういう経営スタイルでいこう」という自分なりの軸を持ち続けることによって、結果として成功に近づくことができるのではないかと思っています。
※このサイトは取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。自己の責任において就職、転職、投資、業務提携、受発注などを行ってください。くれぐれも慎重にご判断ください。




