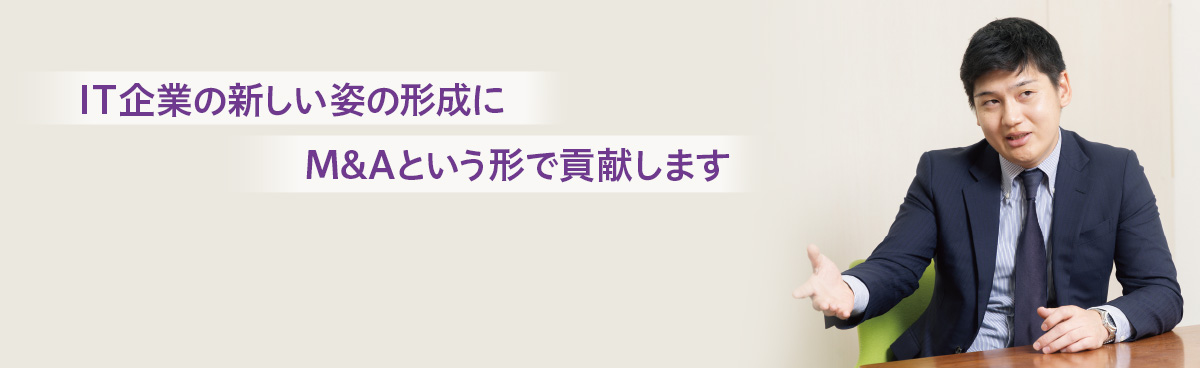INTERVIEW 業界別起業家インタビュー

「集団指導体制」を志向するベンチャー代表が描くM&A戦略
エンジニアだけでなく経営者も、次代のIT企業創りに参加してほしい
株式会社ネクサスホールディングス 代表取締役社長 狩峰 宏行
Sponsored 株式会社ネクサスホールディングス
IT業界では、カリスマ性をもつトップが企業成長をけん引する例が多い。そのなかで、「自らIT企業を経営してきたトップたちに仲間になってもらい、一緒に会社を大きくしていきたい」と語る、異色のITベンチャー代表がいる。ネクサスホールディングスの狩峰氏だ。「集団指導体制」を志向するIT企業の台頭は、業界をどう変えるのか。IT業界のM&A事情に精通するコルウスパートナーズ代表の岡部氏を交えて、語ってもらった。
※下記はベンチャー通信92号(2024年3月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

株式会社ネクサスホールディングス
代表取締役社長
狩峰 宏行かりみね ひろゆき
1969年、愛知県生まれ。高校卒業後、1992年に大手人材派遣会社に営業職として入社。1996年、有限会社ネクサスを設立。翌年、株式会社に組織変更。2015年、株式会社ネクサスホールディングスに社名変更し、代表取締役社長に就任。

株式会社コルウスパートナーズ
代表取締役
岡部 諒平おかべ りょうへい
1996年、東京都生まれ。慶應義塾大学在学中に運送会社を起業し、後に事業譲渡。大学卒業後、大手M&A仲介会社に入社し、M&AコンサルタントとしてIT業界を中心にM&Aの支援を行う。2023年、株式会社コルウスパートナーズの代表取締役に就任。
M&Aを積極的に展開して、グループ売上高は4年で倍増
―事業内容を教えてください。
狩峰:ソフトウェア開発に携わるエンジニアを企業に派遣する事業がメインです。当社のエンジニアが手がける開発の案件は多岐にわたります。たとえば、金融機関において、入出金の処理や取引データの管理などを行う「基幹システム」や、製造業において、生産の数量や工数を計画・管理したりする業務を効率化する「生産管理システム」などです。さらに当社では、グループが担える案件の幅を広げることに注力しています。M&Aを積極的に展開することで、さまざまなスキルをもつエンジニアが仲間になってくれたため、グループ売上高は直近4年で2倍超に急成長しました。
―M&Aの成功事例を教えてください。
狩峰:最近では、IT企業2社にグループインしてもらいました。そのうちの1社は、長年、ソフトウェアの受託開発を手がけてきたビーフィット社。当グループは、顧客先にエンジニアを派遣するビジネスを展開してきたため、受託開発の実績はありませんでした。ビーフィット社がグループインしたことで、事業の幅を広げることができました。また、グループインしたもう1社、NBS社はSESをメインに手がける企業。若手エンジニアが中心の当グループに対し、NBS社には顧客企業のプロジェクトにおける企画や要件定義、基本設計といった上流工程の経験が豊富なベテランエンジニアが多数、在籍。当グループの経験の浅い若手エンジニアにとって、お手本になってくれています。
M&A当時のビーフィット野原社長には、グループイン後、持株会社ネクサスホールディングスの社外取締役に就任してもらいました。私にとっては経営者の先輩として、良き相談相手になってくれています。現在は事業会社の経営に専念してもらっているNBS三上社長にも、いずれはホールディングスの幹部に加わってもらいたいですね。
M&A当時のビーフィット野原社長には、グループイン後、持株会社ネクサスホールディングスの社外取締役に就任してもらいました。私にとっては経営者の先輩として、良き相談相手になってくれています。現在は事業会社の経営に専念してもらっているNBS三上社長にも、いずれはホールディングスの幹部に加わってもらいたいですね。
複数のトップ同士が、互いの判断ミスを是正できる
―グループイン後、両社の経営者にグループの幹部に加わってもらう理由はなんですか。
狩峰:ネクサスホールディングスを、それぞれ事業会社を率いる、専門性をもった経営者が集まる「経営者の集合体」にしたいからです。いわば「集団指導体制」ですね。従来のIT企業では、カリスマ性のあるひとりのトップが強いリーダーシップを発揮するケースが多かった。迅速で果断な意思決定が可能で、急速な成長を実現できるメリットがあります。しかし一方で、ときにカリスマ経営者は周囲の意見に耳を貸さず、独善に陥る危険性がある。たとえば、株価を下げたり、エンジニアの大量退職を招いたりする深刻な判断ミスがあっても、周囲の誰も止められません。
それに対して、当社が目指すのは複数のトップ同士が互いの誤った経営判断を是正できる仕組みです。そうしたグループは、倍々ゲームのような急成長は難しいかもしれませんが、急降下もない。着実に成長を果たせるような強い企業体になりえます。
それに対して、当社が目指すのは複数のトップ同士が互いの誤った経営判断を是正できる仕組みです。そうしたグループは、倍々ゲームのような急成長は難しいかもしれませんが、急降下もない。着実に成長を果たせるような強い企業体になりえます。
M&A買収後の1年で、全社員が退職した失敗も
―岡部さんは、狩峰さんのM&A戦略をどのように評価していますか。
岡部:M&A先の経営者にもジョインしてもらう点で、ネクサスホールディングスは非常によい成功例だと思いますね。従来、IT企業のM&Aにおいては、買い手側がスケールメリットだけを追求する傾向があり、「エンジニアだけジョインしてもらえばいい」という意識が強かった。日本全体でエンジニア不足が深刻化していて、仕事はいくらでもあったことが背景にあります。しかし、AIの活用によるシステム開発プロセス省力化の進展などにより、「単なるプログラマー」レベルのエンジニア需要は減りつつある。反対に、DXを推進する企業が増えてきて、「各分野のビジネスの中身を理解して、最適なシステムを提案し、実装できるエンジニア」へのニーズは高まる一方です。
このような時代には、業界や職種、技術分野など、1つの領域に特化して実績を積んできたIT企業が連合して、それぞれの分野での活動に引き続き取り組みながら、お互いに足りないところを補完し合うような形が、非常に望ましい。いま自律分散型のテクノロジーの進化が話題になっていますが、IT企業もまた、自律分散型に進化するべきときが到来しているのかもしれません。
こうした経営スタイルの強みは、変化の激しい現代において、柔軟かつスピーディに対応できる点です。時代の変化に合わせた組織運営を行うことで、未来の不確定なビジネス環境においても競争力を発揮し続けることができる。ネクサスホールディングスは、その先行例といえると思います。
そして、M&Aにおいて「エンジニアだけでなく経営者にもジョインしてもらう」のは、M&Aを成功させるためにも必要な姿勢といえます。
このような時代には、業界や職種、技術分野など、1つの領域に特化して実績を積んできたIT企業が連合して、それぞれの分野での活動に引き続き取り組みながら、お互いに足りないところを補完し合うような形が、非常に望ましい。いま自律分散型のテクノロジーの進化が話題になっていますが、IT企業もまた、自律分散型に進化するべきときが到来しているのかもしれません。
こうした経営スタイルの強みは、変化の激しい現代において、柔軟かつスピーディに対応できる点です。時代の変化に合わせた組織運営を行うことで、未来の不確定なビジネス環境においても競争力を発揮し続けることができる。ネクサスホールディングスは、その先行例といえると思います。
そして、M&Aにおいて「エンジニアだけでなく経営者にもジョインしてもらう」のは、M&Aを成功させるためにも必要な姿勢といえます。
―詳しく教えてください。
岡部:いま、IT業界ではM&Aが非常に盛んになっています。これはおもに、売り手側の事情によるものです。従来のIT業界では、事業規模の拡大に従って、IPOによるイグジットを目指すのが一般的でした。しかし、SESのような労働集約型の企業は、自社サービス開発・販売のような企業と比べて、株価の面で評価されづらくなっています。その意味で、IPOの難易度は上がっているといえますね。そのため、M&Aによるイグジットを志向する動きが増えているのです。
しかし一方で、買い手側に目を転じてみると、希望通りの企業買収に成功している企業は多くありません。特に、大手企業に顕著ですが、「エンジニアの数を増やすため、この時期までに必ず1社を買収する」といった期限を設けて、「買う前提」の姿勢でM&Aにのぞむ。そのため、企業の「本来の価値」を適切に評価できず、非常に割高な額で買ってしまったり、過去に不祥事を起こした企業を見抜けずに買ってしまったりといった失敗を犯してしまいがちです。これに対して、「経営者にも仲間になってもらいたい」という姿勢で売り手企業を精査すれば、財務状況や法務リスク、経営者とエンジニアの信頼関係の深さなど、さまざまなことがわかってくる。しかも、売り手側の経営者も、M&A後のグループ全体に対して経営責任を負い、運命共同体になるわけですから、ウソやごまかしもなく、誠実に情報を公開してくれます。その結果、M&Aが成約にいたりやすいのです。
狩峰:じつは、当社もかつて「エンジニアの数を増やしたい」とあせるあまり、M&Aで大きな失敗をしたことがあります。あるとき、知り合いの経営者から「SES事業を売却したい」と、1億円近い買収額を「言い値」で提示されました。よく知る知人から提案されたものでしたから、「信用できる案件だろう」と、よく精査もせずに買収したのです。しかし、1年もたたないうちに、約50名の全社員が申し合わせたように退職してしまいました。どうやら、元の経営陣に対する長年の不満が募っており、社員の多くが退職の意向を固めていたようです。エンジニアとのコミュニケーションをもっと密に行うなど、M&A後のフォローが足りなかった点は私も反省しています。これ以降は、「買収先のトップと一緒に経営しよう」と考えるようになりました。
しかし一方で、買い手側に目を転じてみると、希望通りの企業買収に成功している企業は多くありません。特に、大手企業に顕著ですが、「エンジニアの数を増やすため、この時期までに必ず1社を買収する」といった期限を設けて、「買う前提」の姿勢でM&Aにのぞむ。そのため、企業の「本来の価値」を適切に評価できず、非常に割高な額で買ってしまったり、過去に不祥事を起こした企業を見抜けずに買ってしまったりといった失敗を犯してしまいがちです。これに対して、「経営者にも仲間になってもらいたい」という姿勢で売り手企業を精査すれば、財務状況や法務リスク、経営者とエンジニアの信頼関係の深さなど、さまざまなことがわかってくる。しかも、売り手側の経営者も、M&A後のグループ全体に対して経営責任を負い、運命共同体になるわけですから、ウソやごまかしもなく、誠実に情報を公開してくれます。その結果、M&Aが成約にいたりやすいのです。
狩峰:じつは、当社もかつて「エンジニアの数を増やしたい」とあせるあまり、M&Aで大きな失敗をしたことがあります。あるとき、知り合いの経営者から「SES事業を売却したい」と、1億円近い買収額を「言い値」で提示されました。よく知る知人から提案されたものでしたから、「信用できる案件だろう」と、よく精査もせずに買収したのです。しかし、1年もたたないうちに、約50名の全社員が申し合わせたように退職してしまいました。どうやら、元の経営陣に対する長年の不満が募っており、社員の多くが退職の意向を固めていたようです。エンジニアとのコミュニケーションをもっと密に行うなど、M&A後のフォローが足りなかった点は私も反省しています。これ以降は、「買収先のトップと一緒に経営しよう」と考えるようになりました。
リーマン・ショック時にも、「人を大切にする経営」を貫く
―狩峰さんが、経営で大事にしている考えを教えてください。
狩峰:「人を大切にする経営」です。同業他社のなかには、エンジニアを取り換えのきく「コマ」のように扱うところもあると聞きます。当社では、リーマン・ショック時、多くの競合と同様に売上を大きく落とし、月当たり数百万円の赤字が数ヵ月続きました。お客さまからの仕事が減り、エンジニアに案件を割り振れない事態になりました。しかし、エンジニアに一時休業してもらった際に、公的な助成金を活用するなどして踏ん張り、決してエンジニアを解雇しませんでした。エンジニアとその家族の生活を守ることを優先したからです。「人を大切にする経営」という信念は守っていきたいと考えています。
―ネクサスホールディングスの今後のビジョンを教えてください。
狩峰:M&Aによって、エンジニア派遣から請負開発まで、事業の幅を広げることができました。これからはM&Aで加わってくれた社員も含めて、グループ内の人材を次代の経営者に育てたいですね。「経営者の集合体」をつくり、次世代のIT企業のあり方を模索したいです。当グループの理念に共感する企業には、ぜひ次代のIT企業創りに参画してほしいですね。
―岡部さんは、IT業界のM&Aをどのようにサポートしていきたいですか。
岡部:独立した経営者がグループの事業会社を担うことで構成される「集合体」は、持株会社からの過度の干渉を防ぐことで各経営者の強みを損なわずに、かつ、グループ全体の成長に向けて、結束を強化する可能性があると思います。こうしたIT企業の新しい姿の形成に、M&Aという形で貢献したいですね。
株式会社ネクサスホールディングス 企業情報
| 設立 | 1996年4月 |
|---|---|
| 資本金 | 7,029万1,000円 |
| 売上高 | 19億5,000万円(2024年9月期:連結) |
| 従業員数 | 253名(グループ全体、2025年3月現在) |
| 事業内容 | IT技術者派遣、ソフトウェア開発、機械設計開発 など |
| URL | http://nexus-hld.com/ |
株式会社コルウスパートナーズ 企業情報
| 設立 | 2013年11月 |
|---|---|
| 資本金 | 500万円 |
| 事業内容 | M&Aアドバイザリー・M&A仲介、経営コンサルティング、PMIコンサルティング、そのほかに付帯する業務 |
| URL | https://corvus-co.jp/ |
※このサイトは取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。自己の責任において就職、転職、投資、業務提携、受発注などを行ってください。くれぐれも慎重にご判断ください。